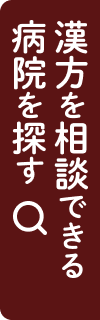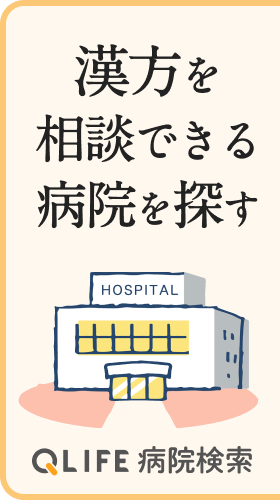記者アーカイブ

Vol.1 民間薬と漢方薬の違い|くらしと生薬
日本のくらしに古くから根づいている生薬の話をしてほしいとのご要望に応え、医師である筆者と、薬学者で歴史にも造詣の深い帝京平成大学薬学部の鈴木達彦先生より、それ…
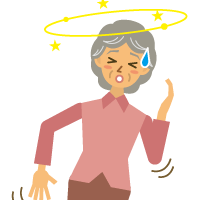
めまい経験者のめまい専門医・新井基洋先生に聞く Vol.1 高齢者に多い、フレイルを合併しためまいとの付き合い方
日本人の約2割が、めまいの症状を抱えているといわれます。しかし、「めまい」と、ひとくちに言っても、ふわふわした浮遊感を覚えることもあれば、グルグルと目が回るよう…

柴苓湯(さいれいとう)
柴苓湯は、抗炎症作用を持つ小柴胡湯と、利水作用を持つ五苓散を合わせたものといわれています。しかし、製法の違いから、柴苓湯のほうが小柴胡湯+五苓散よりも穏やかに…

十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)
十全大補湯は、体の働きを補う補剤のひとつで、名前の通り10の生薬から構成されています。補剤にはほかに、補中益気湯や人参養栄湯などがあります。

人参養栄湯(にんじんようえいとう)
人参養栄湯は、体の働きを補う補剤のひとつで、全身の栄養状態を改善する漢方薬です。十全大補湯と同じく、がんなどで体力や免疫機能も落ちてしまったときに用いられます…

コロナ禍のストレス対策 Vol.2 病気になる前の未病の段階で対処をしておく
長期化する新型コロナウイルス感染症の流行は、私たちに多くの変化をもたらしました。その変化や先の見えない状況のもと、多くの人がストレスを抱えています。小さなスト…

コロナ禍のストレス対策 Vol.1 心と体はつながっている 「正しく恐れる」ことが大切
新型コロナウイルス感染症の流行が長期化する中、生活の変化や先の見えない状況が続く不安などからストレスを抱える人が増えています。

<外来でよく使われる漢方薬 編集後記> もとは急性期に使われていた!「人間の身体防御システムを正常化する」漢方薬
医療機関へ行ってお薬を処方されると、その中に漢方薬が含まれていることが増えてきました。実際に、漢方薬を処方している医師は89%にも上る1)といわれており、漢方薬で…

コラム:人によって異なる漢方薬の作用
漢方薬がもたらす効果について、西洋薬と比較しながらもう少し詳しく解説します。実は漢方薬には「服用した人と呼応(反応)した時だけ薬剤の作用をする」という特徴があ…

麻黄湯(まおうとう)
麻黄湯の名は、その主成分である麻黄から付けられたと考えられています。また、A型インフルエンザウイルスの増殖を抑制する研究結果も報告されており1)、現在初期のインフ…

葛根湯(かっこんとう)
一般的に葛根湯は「初期のかぜ薬」として用いられることの多い漢方薬ですが、かぜ症状の改善については、切れ味が鈍いことも少なくありません。

半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)
半夏瀉心湯の「瀉心」とは、「みぞおち付近のつかえを解消する」という意味で、胃腸炎や消化不良、嘔吐、二日酔いなどの消化器疾患に幅広く用いられます。また最近では、…

牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)
牛車腎気丸は、高齢の特に男性で、夜に何度もトイレに行くというというような頻尿の改善によく用いられます。また、下半身のしびれ、坐骨神経痛など、主に「下半身」の病…

五苓散(ごれいさん)
五苓散は、体内の水分代謝の異常を調整する代表的な漢方薬で、むくみのある状態では利尿作用を、脱水の状態だと水分を保持するという働きを持っています。最近の研究では…

麦門冬湯(ばくもんどうとう)
麦門冬湯は、中国後漢末期の官僚で医師である張仲景(ちょう ちゅうけい)によって書かれた中国の古典医学書『金匱要略(きんきようりゃく)』を出典とした薬で、咳を鎮め…

加味逍遙散(かみしょうようさん)
加味逍遥散は、当帰芍薬散、桂枝茯苓丸と並んで「女性の三大処方」と呼ばれ、女性に多く使われている漢方薬のひとつです。加味逍遥散は、イライラ、不眠、疲れやすいなど…

芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)
芍薬甘草湯はその名の通り、芍薬と甘草という2種類の生薬から作られた漢方薬です。芍薬甘草湯は、こむら返り(腓腹筋けいれん)のような、筋肉のけいれんや収縮に伴う痛み…

六君子湯(りっくんしとう)
六君子湯は、漢方薬の代表的な胃薬のひとつです。胃粘膜を保護する作用や、胃の内容物の排出を促進させる作用、抗ストレス作用など、ひとつで多くの作用を持ちます。