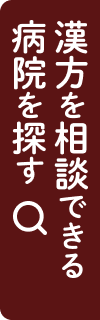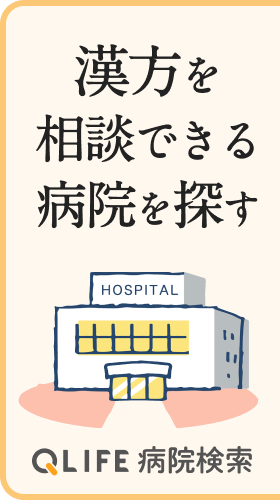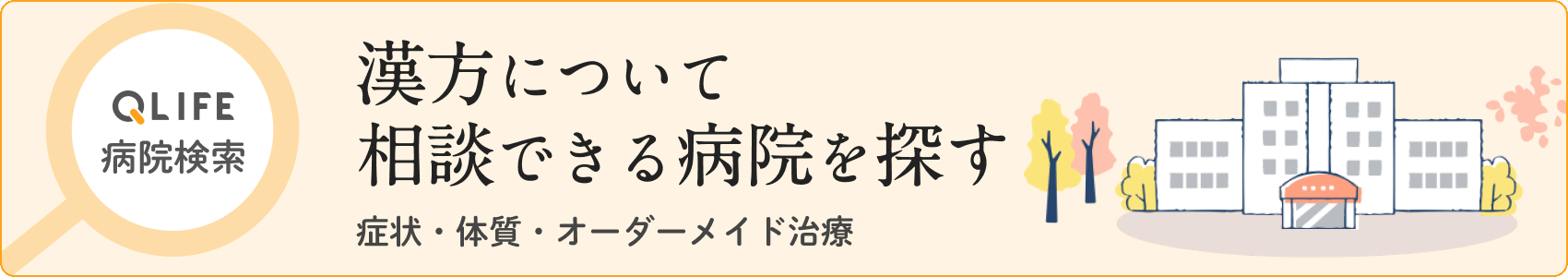十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)
構成生薬
- 黄耆(おうぎ)
- 桂皮(けいひ)
- 地黄(じおう)
- 芍薬(しゃくやく)
- 蒼朮(そうじゅつ)
- 川芎(せんきゅう)
- 当帰(とうき)
- 人参(にんじん)
- 茯苓(ぶくりょう)
- 甘草(かんぞう)
作用の特徴
がんや重病で免疫機能がひどく落ち、体力の消耗が激しいときに用いる
長期の服用が必要
対象となる症状
- 病後/術後の体力低下
- 食欲不振
- 疲労倦怠
解説
十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)は、体の働きを補う補剤のひとつで、名前の通り10の生薬から構成されています。補剤にはほかに、補中益気湯(ほちゅうえっきとう)や人参養栄湯(にんじんようえいとう)などがあります。
がんや重病を患って、体力も免疫力も落ちてしまっているときには、病気にかかりやすくなったり、消化機能の低下から食欲不振の症状も現れたりすることがありますが、十全大補湯を服用することで、体力と食欲が徐々に回復していきます。
そのため、最近では、術後の体力改善、化学療法や放射線治療の副作用の軽減、緩和医療など、がん治療の現場でも使われるようになっています。
また、肝細胞がんを外科手術で除去した患者に対し、十全大補湯の投与群で有意に腫瘍の発生を延長できたという臨床研究1)があります。
エビデンス情報
肝硬変に対する十全大補湯投与による肝細胞がんの予防効果
B型およびC型肝炎ウイルスによる肝硬変の患者72例に対し、それぞれ十全大補湯投与群、非投与群とでランダム化比較試験を行いました。肝硬変全体での累積生存曲線は両群で有意差を認めませんでしたが、十全大補湯投与群では、生命予後が良好な傾向が認められました。また、肝硬変全体では、十全大補湯群で肝細胞がん発生が抑制され、C型肝硬変の場合には、有意に肝細胞がん発生が抑制されました2)。
がん患者の放射線治療時の副作用症状に対する十全大補湯の有効性と安全性
胸部ないし腹部に放射線照射を施行した83例に対し、十全大補湯投与群、非投与群とでランダム化比較試験を行い、がん患者の放射線治療に伴う副作用症状に対する十全大補湯の有効性と安全性を評価しました。照射開始後、両群で白血球数、赤血球数、血小板数、血液生化学検査には差を認めませんでしたが、投与群において食欲不振は、4〜6週で改善傾向、5週で有意差を認め、全身倦怠感は4週で、悪心・嘔吐は5週で、下痢は3〜5週で差を認めました3)。
 QLife漢方 閉鎖のお知らせ
QLife漢方 閉鎖のお知らせ