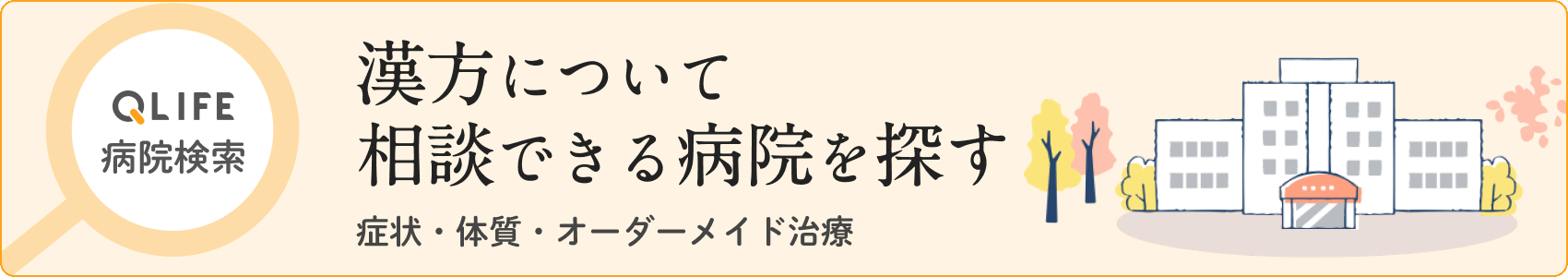Vol.2「日本漢方」の成り立ち ~中国の古典的医学から日本の伝統医学へ、そして……~|漢方薬の歴史と未来

――漢方は中国の医学ではありません、日本独自の医学です。
このサイトにお越しになっている皆さんには、ひょっとしたらもうおなじみの言い回しかもしれません。漢方は古代中国医学を源流として中国より日本にもたらされたのを皮切りに、その後も両国の宗教および学術交流、そして交易を介してやってくる「中国の最新医学」を取り入れ、日本の気候風土や日本人の体質、日本で入手可能な生薬の種類や量などに応じてそれらを応用しながら発展してきています。「日本独自の医学」というには確かにそれだけでも十分でしょう。
ただ、それ以外にも「日本漢方の特徴」「日本漢方の歴史的経緯」があります。また一方で「古典的な中国医学と現代中医学の間に生じた違い」もあり、現代の日本漢方と現代中医学はかなり様相を異にしています。そして近年、中医学が日本に紹介されたり臨床で応用されたりするケースが増えてきたことで、かえって混乱することも増えてきています。
――というわけで、本稿では「日本漢方」の成り立ちと特徴について、今一度整理したいと思います。
奈良時代に「外来の医学」が到達、僧侶によって広められていく
日本に「外来の医学」が到達したのは、実は奈良時代以前にさかのぼります。414年に新羅から名医が来朝して天皇の病気を治療したなどの記述が『日本書紀』にみられるのを始めとして、中国および朝鮮半島で行われていた医学が(仏教などとともに)朝鮮半島を経由して日本にもたらされてゆくのです(私は学生時代、こと伝統医学については“中国は親の国、朝鮮は兄の国なのである”と習いました)。中国からの直接の知識の導入は、奈良時代から平安時代にかけての遣唐使を介してのことでした。当時、僧侶たちの中には仏道実践の一環として、煎じ薬を用いて病気治療を行うものが多く、医術は僧侶たちによって学ばれ、広められてゆきました。701年に施行された大宝律令には唐の制度の模範とした医療制度が定められ、天平6(754)年に来日した鑑真和上は、仏典のほかに多くの薬物を携えてきました。奈良の正倉院に収められた御物の中には甘草(かんぞう)、人参(にんじん)、大黄(だいおう)、桂心(けいしん)=桂皮(けいひ)、厚朴(こうぼく)など、現代でも用いられる生薬が多く含まれ、これらは遣唐使がもたらしたもののほか、鑑真和上が携えてきた、まさにその品が含まれているとされています。永観2(984)年に丹波康頼が編纂した『医心方』は日本人による最古の医学書とされますが、これは日本独自のものではなく、隋唐時代の中国の医薬書をとりまとめたものでした。
「漢方」と呼ばれるのは江戸期に入ってから
その後、鎌倉~室町中期には宋代の医学が、それ以降には明代の医学が導入され、実践されていきますが、江戸中期以降、「日本独自路線」が立ち上がりはじめます。これまで日本に導入されたさまざまな時代の「中国医学」を学んだ医師たちが、病の本質とは何か、治療の本質はどこにあるかといった、多くの自説を打ち立て始めたのです。
そのうち「後世派」と呼ばれる流派は比較的古く、江戸時代初期には確立しており、明代中国の李朱医学※1を基本とするものでしたが、それに対してさまざまな流派が発生していきます。
陰陽五行説や臓腑経絡論※2を重視する「後世別派」と呼ばれる流派、循環すべき気が環境や飲食、精神的なストレスなどによって腹の中に滞留することがすべての病の根源であるとする「一気滞留論」、すべての病はひとつの毒に由来するとする「万病一毒説」、人体は気血水の循環によって養われ、毒によってそれが滞れば病が生じるとする「気血水論」などなど……、その中で『傷寒論』や『金匱要略(きんきようりゃく)』など、漢代に成立した(つまり、医学としてはごく初期の)処方集に掲載された処方を中心として用いた医師たちは「古方派」と総称されました。滋養強壮を重んじる「後世派」に対し、病の根源はなんらかの邪毒によるものであり、“毒をもって毒を制す”式の薬の使い方をすること、時代を経るにつれて“洗練”されていった中医学理論に基づく新しい処方ではなく、よりプリミティブな処方を用いることがその特徴です。
なお、漢方が「漢方」と呼ばれるようになったのは江戸期に入ってからのことです。鎖国政策を敷いていた日本に長崎の出島を通じて入ってきた西洋医学を「蘭方」(オランダ=和蘭陀と表記していたことから)と称したのに対し、旧来の中国にルーツを持つ医学を“漢代に成立したものが入ってきた医学”として「漢方」と称したのが始まりです(漢代の中国からリアルタイムで日本に導入された……というわけではないので注意!)。「漢方」の語は日本でしか使用されておらず、中国や台湾では、古代中国医学をルーツとする伝統医学は「中医」と称しています。実のところ台湾では「漢方」という表示も見かけることはあるのですが、これは“ほかの「中医」とは違う、日本式にアレンジしたちょっとお洒落な伝統医学”というアピールの意味合いがあるようです(台湾では、日本は先進的・高品質・お洒落……といったイメージがあります)。
※1:李朱医学
中国の金(きん)・元(げん)の時代(12~14世紀)に成立した古代中国医学の一学派。提唱者のひとりである李杲(りこう)は、病気の原因は体外ではなく体内の環境にあると考え、朱震亨(しゅしんこう)は李杲の考えを発展させて治療法などを生み出した。この二人の医説を李朱医学と呼ぶ。日本における李朱医学の開祖・田代三喜(さんき)は、室町時代に中国に留学して修めて帰国。その弟子の曲直瀬道三(まなせどうさん)は多くの後進を指導、李朱医学は日本で進化を遂げ江戸時代初期まで日本の医学において重要視された。滋養・強壮を目的として臓腑を温める治療法を多く用いるのが特徴。
※2:臓腑経絡論
人体やその機能の捉え方のひとつ。人体のさまざまな機能を概念化し、肺(体外よりの気の取り込みと、体の内外を区別する境界としての機能を併せて称する)、腎(水分の排泄にも関わるが、同時に親から受け継いだ先天的な気の貯蔵や生殖関係の機能もつかさどる。東洋医学的には後者の方が重要な機能である)などと名づけた「臓腑」と、それらをつなぎ、生命活動を維持するためのエネルギーを循環させる経路である「経絡」を重要視して人体のあり様を説明する。経絡上のエネルギーの滞りが生じやすい場所を経穴(けいけつ、ツボ)として刺激することで治療を行なう指圧や鍼灸などの物理療法は、この理論を重要視している。
強烈な逆風から復興し、新しい「漢方」の歴史が幕を開ける
その後、幕末から明治にかけて、漢方に対する強烈な逆風が吹くことになります。明治新政府と密接な関係を持っていたのは西洋医学者であり、その新政府が西洋文化を取り入れたこととも相まって、漢方は衰退していきます。そして新政府の発布した医師免許規則で、西洋医学のみを範囲とした医師開業試験に合格しなければ医業が不可となるにあたり、漢方は一時期、完全に日本の医学・医療の表舞台から姿を消します。日本の漢方を細々と受け継いだのはごく一部の医師、そして薬剤師(こちらは「漢方薬を直接販売していた」ことから、医師よりも漢方に関わる人が多かったとされます)でした。
昭和初期になってようやく、西洋医学を修めた一部の医師たちが治療医学としての漢方の有用性に着目するようになりました。このとき、医師たちが取り上げたのが古方派の漢方であったことから、現在の日本では伝統医学の流派のうち、古方派の漢方をベースとして、「後世派」などで用いられた“新しい”処方も用いるものとなっています(一方、現代の中国や台湾の中医学はというと、それまでの時代の種々の中医学理論を統合し、一部西洋医学の考え方も取り入れたものとなっています)。
漢方の復興がいわゆる「科学的根拠に基づいたもの」ではなく「一部の医師たちが有用性を見出した」ことによって行われたことから(事実、漢方処方の承認は“長年の使用経験に基づいて”行われています)、漢方は果たして科学的な医薬品かということに疑問が呈されることも確かにあります。しかし「一度は廃れかけても、治療のツールとして有用であるとしてわざわざ再興させられ、ついには医学・薬学教育のコア・カリキュラムに組み込まれるに至ったもの」は、「現代のサイエンスとは異なる方法論で人間の健康にアプローチし、現代のサイエンスが取り落としている部分で人を救い得るもの」と見なしてもよいといえるのではないでしょうか。
もちろんサイエンスの手法によって漢方の作用機序を解き明かそうとする研究も、たゆまず進められています。古くから伝わってきた「漢方というものがたり」が科学というもうひとつの言葉で語り直されてゆくところに、漢方の新しい歴史が開けてゆくのだともいえます。
日本薬科大学講師(漢方薬学科)

 QLife漢方 閉鎖のお知らせ
QLife漢方 閉鎖のお知らせ