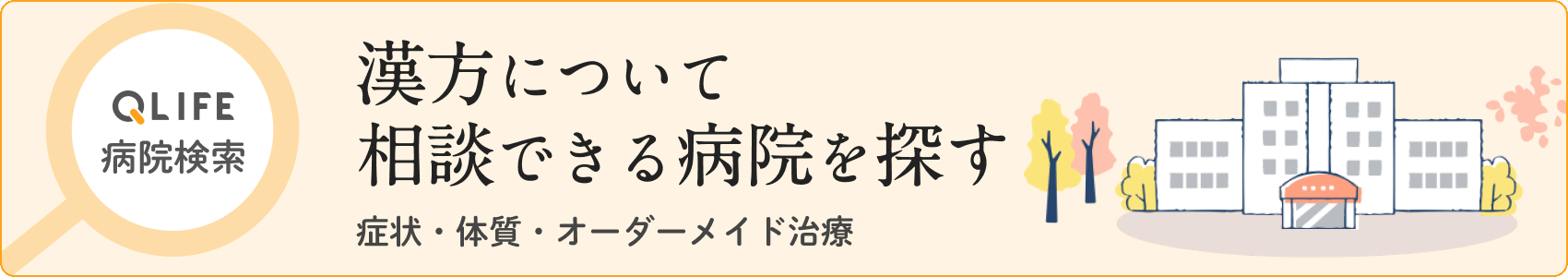新型コロナの重症化を抑制する可能性のある漢方薬 そのエビデンス構築までの道のり
新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)のパンデミックから2023年6月で丸3年以上が経過し、この感染症についても複数の新たな治療薬が登場しました。しかし、それらはいずれも適応や副作用など様々な制限があり、感染者の誰もが服用できる治療薬はほとんどないのが実状です。そうした中で2022年11月、日本東洋医学会が主導した多施設共同での無作為化比較試験という手法による軽症・中等症の新型コロナ患者に対する漢方薬の葛根湯(かっこんとう)と小柴胡湯加桔梗石膏(しょうさいことうかききょうせっこう)を使った研究結果が医学誌「Frontiers in Pharmacology」に掲載されました。
その結果は、この2つの漢方薬を従来の治療(解熱薬、咳止め薬、去痰薬)などと併用すると、従来の治療のみよりも発熱改善までの期間が短縮され、重症化を抑制する可能性があるというものでした。今回、この研究を中心になって進めた東北大学大学院医学系研究科漢方・統合医療学共同研究講座特命教授の髙山真先生にこの研究の経緯や意味づけについてお話を伺いました。前編では、研究に至った経緯やそのご苦労を紹介します。(村上和巳)
「スペイン風邪」時代からあった漢方薬での感染症治療

―はじめに、今回の臨床研究を企画した意図を教えてください
髙山 今回の臨床研究を検討し始めたのは、2020年当初の新型コロナによる肺炎を発症した人の致死率が高かった時期です。当時は今のように新型コロナに特異的な治療薬もなく、私たちは丸腰で戦わなければならない状態でした。このため各方面で行われていたのが、有効性が期待できそうな既存の薬を使った臨床研究です。
現在、私たちが主に取り組んでいる漢方薬による治療の源流は中国の伝統医学(中医学)ですが、その古典医学書「傷寒論(しょうかんろん)」には、今では私たちが感染症と認識している病気に関して生薬(漢方薬)を使った治療法が記述されています。一般の人が慣れ親しんでいる西洋薬の治療とは異なるものの、漢方薬は1000年超の歴史を持つ感染症の治療経験があるわけです。そこで新型コロナでも何らかの可能性があるのではないかと考えたのが臨床研究のきっかけです。
―ウイルス感染症に対する漢方薬治療の実績はあるのでしょうか?
髙山 代表例が季節性インフルエンザです。例えば約100年前に全世界で流行した通称「スペイン風邪」は、今ではA型インフルエンザに分類されるインフルエンザウイルスH1N1亜型が原因と分かっています。しかし、当時は正確な原因は不明でこの感染症に特化した治療法も皆無でした。新型コロナ当初と同じ丸腰状態だったわけです。
この時、日本では徳川将軍家の典医も務めた漢方医・浅田宗伯氏の弟子だった木村博昭(きむら はくしょう)氏が漢方薬の柴葛解肌湯(さいかつげきとう)を用いて治療した記録が残っています。また、同時期に漢方家(明治政府が発行した医師免許は保有していなかった)だった森道伯(もり どうはく)氏は、このスペイン風邪を症状別に3つに分類し、胃腸型には香蘇散加茯苓白朮半夏(こうそさんかぶくりょうびゃくじゅつはんげ)、肺炎型には小青竜湯加杏仁石膏(しょうせいりゅうとうかきょうにんせっこう)、脳症型には升麻葛根湯加白朮川芎細辛(しょうまかっこんとうかびゃくじゅつさいしん)を用いて患者の対応に当たった記録もあります。
漢方薬の成分研究で示された抗ウイルス効果
―ミクロな観点から漢方薬がウイルス感染症に有効という報告はあるのでしょうか?
髙山 今回の新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスは遺伝情報としてRNA(リボ核酸)を有するRNAウイルスで、ヒトの体内に入ると、細胞に結合して自身のRNAをその中に潜りこませ、ヒトの細胞増殖機能を乗っ取って新たなウイルスを作り、それが細胞内から飛び出して新たな細胞内に入り込むという増殖サイクルを繰り返します。生薬・麻黄が主成分の麻黄湯は、インフルエンザウイルスがヒトの細胞に入り込んで自らのRNAを放出(脱殻)する前後の働きを抑えることが報告されています1)。その意味でRNAウイルスである新型コロナウイルスでも有効性が示せると考えるのは論理的には自然です。
実際、その後の研究で今回の新型コロナウイルスについては、生薬の桔梗に含まれるプラチコジンDと呼ばれる成分が、ヒトの細胞にウイルスが入り込む際に起こる膜融合という現象を防ぐという報告2)、小柴胡湯を構成する生薬・黄芩(おうごん)に含まれるバイカレインという成分がウイルスの増殖に必要なプロテアーゼと呼ばれる酵素の働きをブロックするという報告3)もあります。ちなみにこのプロテアーゼを阻害するという効果で承認された西洋薬が現在新型コロナ治療薬として使われているニルマトレルビル/リトナビルです。
研究の立案までの紆余曲折
―今回の臨床研究で葛根湯と小柴胡湯加桔梗石の2種類の漢方薬を使った理由を教えてください。
髙山 まず、新型コロナの症状を見ると、多くが高熱を呈します。中医学では急性感染症について2つのとらえ方があります。1つは「傷寒」という考え方で、寒気を感じてから発熱し、関節痛などにも至る症状を指します。もう1つは「温病(うんびょう)」で、この場合は発症当初から熱が出て、喉が腫れて痛みを生じ、症状が長引くのが特徴です。温病を西洋医学的にとらえると、体内の臓器で炎症が起こっている状態です。
今回のパンデミック当初、中国では「新型コロナは傷寒か?それとも温病か?」の論争がありました。一般的には傷寒の考え方が適応されるのかもしれませんが、私たちが診察した感染者の中には約40℃の発熱が1週間続いた事例などもありましたので、このケースは温病と解釈できます。そこで私たちは、新型コロナは傷寒と温病の両方の側面があると捉えました。そうなると、漢方薬の治療に慣れている医師ならば、ウイルス性呼吸器感染症に有効な麻黄(まおう)、傷寒での発熱を改善する生薬の桂枝(けいし)、温病での発熱を改善する石膏(せっこう)、こじらせた風邪などに使われる抗炎症作用を持った小柴胡湯(しょうさいことう)の生薬成分のすべてが含まれているならば、新型コロナに有効ではないだろうかと考えます。この条件を満たす漢方薬は、先ほどスペイン風邪の時に使われた記録がある柴葛解肌湯です。
―それではなぜ柴葛解肌湯ではなく、葛根湯と小柴胡湯加桔梗石膏となったのですか?
髙山 柴葛解肌湯を販売している製薬企業は1社のみで、私たちが計画していた無作為化比較試験という手法に協力できる企業体力や研究のプロトコール作成に協力できる社内研究者もいないという現実がありました。そこで柴葛解肌湯の成分を別の漢方薬でほぼ再現することを考え、今回の葛根湯と小柴胡湯加桔梗石膏の併用に落ち着きました。
―研究デザインを考えた際の苦労はどうでしたか?
髙山 我々はパンデミック当初の2000年春に研究を企画しましたが、当時国内外で行われていた治療薬の臨床研究の主要評価項目は、ほとんどが入院や死亡のリスク軽減効果で、2次的に症状改善を評価していました。
当時の主流の武漢株の重症化率は20%前後で、この病態で入院や死亡のリスク軽減効果を主要評価項目にすると、事前の統計学的試算では最低300人、可能ならば700~1000人の臨床研究参加者が必要と分かりました。実際、後に新型コロナに対する重症化軽減効果が認められて世界で初めて承認された飲み薬(抗ウイルス薬)のモルヌピラビル(商品名:ラゲブリオ)の臨床試験は約700人の感染者で行われています。
しかし、当時の日本では感染者自体が少なく、私たちがいる宮城県では週に数人発生する程度で、文書で同意取得ができる臨床研究参加者を300人も集めることは相当困難と判断しました。差し迫った状況を考えると、なるべく早く結果を公表する必要もありました。
そのためより少数の参加者でも評価可能な発熱、倦怠感、呼吸器症状である咳、痰、息切れなどの症状改善を主要評価項目にし、2次的に入院や死亡のリスク軽減効果を評価するという当時の主流とは逆の立て付けを取らざるを得ませんでした。
苦戦した研究参加者のリクルート
―研究結果を見ると、漢方薬を服用していた参加者でも比較的多くの割合で西洋薬の解熱薬や咳止め薬といった従来の治療薬を併用しています。
髙山 当時は新型コロナで亡くなる確率は今以上に高い時期でした。にもかかわらず、参加者に現状で行える治療をせず、効果を確認しようとしている漢方薬のみを割り当てる研究を行えば倫理的に問題視され、臨床研究実施の可否を判断する大学の倫理審査委員会も認めない可能性がありました。
このため一定の基準を設けて症状を緩和する解熱薬や咳止め薬などの従来の治療を行った参加者を、そのまま従来の治療のみ行う人のグループと、従来の治療に漢方薬を併用する人のグループに分けて比較することで、症状改善の上乗せ効果を評価する設定となりました。
―現在新型コロナの治療薬として承認されている飲み薬の服用期間はいずれも5日間です。今回の臨床研究では漢方薬2種類の服用期間がより長期の14日間だった理由を教えてください。
髙山 当初の武漢株からデルタ株までは、重症化の境界線は発症から1週間前後でした。臨床研究では2次的とはいえ入院・死亡リスクも評価していることを踏まえ、投与期間は14日間としました。
もっとも現在主流となっているオミクロン株では、国民に広くワクチン接種が行き渡ったことなども影響して、重症化率は当初に比べ大幅に低下しています。その意味では現在臨床で使用するならば、5日程度の服用でも差し支えないだろうと考えています。
―実際の臨床研究開始後にはどのような苦労がありましたか?
髙山 やはり参加に同意していただける感染者を見つける点に苦労しました。今回、同意いただけたのは161人ですが、実際には500人ほどの感染者に協力をお願いする説明をしています。
実際、激しい咳が止まらない、発熱が40度近くあるという感染者に研究の説明をして同意を取得しようとしても「咳がひどいので、研究はどうでもいいので咳止め薬を出して下さい」などと言われることは多かったですね。
そもそも臨床研究のことを説明している私たちも申し訳なく感じるほど、パッと見で症状がつらそうな人たちが多かったのが現実です。参加していただいた皆さんには今も本当に感謝しています。
後編では、この研究結果の意味することや今後この結果を実際の医療現場でどのように活用するかについて引き続き髙山先生に話を伺います。
- 参考
-
- Mantani N, et al. Antiviral Res 1999; 44(3): 193-200
- Kim TY, et al. Exp Mol Med 2021; 53(5): 956-972
- Liu H, et al. J Enzyme Inhib Med Chem 2021; 36(1): 497-503

東北大学大学院医学系研究科 漢方・統合医療学共同研究講座 特命教授/東北大学病院 総合地域医療教育支援部 副部長、准教授/同病院 漢方内科 副診療科長
 QLife漢方 閉鎖のお知らせ
QLife漢方 閉鎖のお知らせ