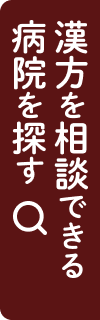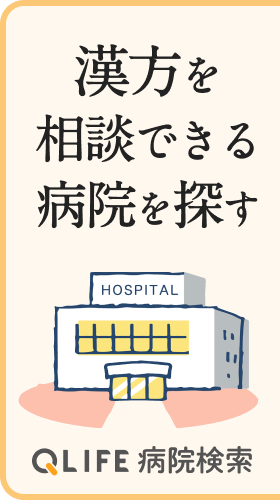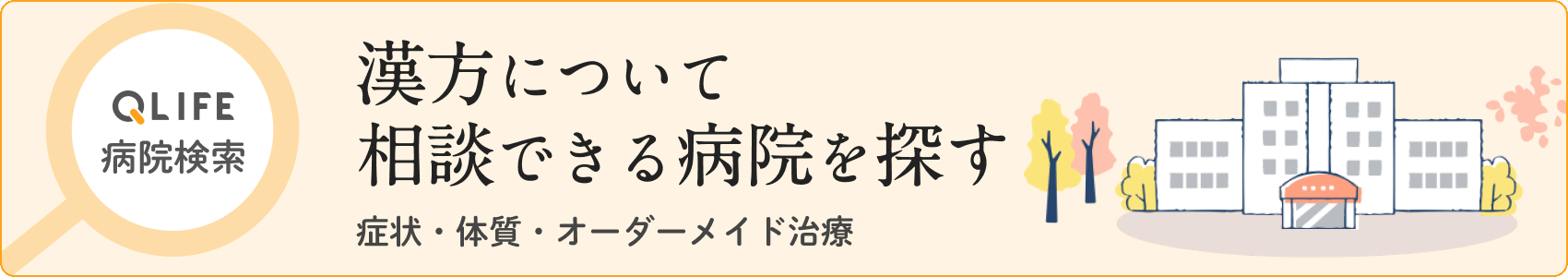漢方で支える妊娠・出産のステップ ~産婦人科医が解説する症状別処方と未来への展望~
産前産後や妊娠・出産時の漢方について、前編では現代と過去の女性の心身の変化や漢方治療のメリットなどをお伝えしました。後編では、より具体的な時期や症状に対する効果的な漢方薬の紹介、その効果の目安、女性における漢方治療の将来的な展望について解説します。前編に引き続き、かしわの葉レディースクリニック院長で産婦人科・漢方婦人科医の岡村麻子先生にお話を伺いました。
産前産後と妊娠・出産時の漢方薬使用例

妊娠中および産後(産褥)の女性の状態とは
具体的な症状、不調とそれに有効な漢方薬を紹介する前に押さえておきたい点として、岡村先生は、妊娠中および産後は虚証の状態を挙げています。
「前編で、現代女性の多くが虚証という、心身のバランスが崩れ、体に必要なものが足りていない状態にあることをお話しましたが、妊娠中ならびに産後は、誰でも基本的に虚証となります。つまり、もともと虚証の方にとっては、さらに状態が悪化するわけで、妊娠・出産・産後の各症状や不調がより強く表れやすくなります」(岡村先生)
時期ごとの症状・不調を緩和・改善する漢方薬
1)妊娠前から出産まで~妊娠しやすい体づくりも含め全妊娠期間を通じて有用な基本薬
「保険適用のエキス製剤から選ぶ場合、妊婦さんへのファーストチョイスは当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)です。これは女性三大漢方のひとつで、主に血液に関する異常(血虚)を改善する処方です。月経異常や不妊症など妊娠前の時点から広く用いられ、妊娠に至っても安胎薬として使い続けられます。
胎児毒性に関する安全性が確認されており、子宮収縮や腹痛、動悸、皮膚症状、痔、むくみ、子宮内胎児発育不全1, 2)、妊娠高血圧症の予防、不育症3)に有効とされ、子宮内膜症や腺筋症合併妊娠の経過を助けるとの報告もあります4)。
多くの妊婦さんに適した当帰芍薬散ですが、胃腸虚弱や悪阻(つわり)で飲めない方の場合は六君子湯(りっくんしとう)や補中益気湯(ほちゅうえっきとう)などの胃腸機能を改善する処方、あるいは、後述するつわりの漢方処方を選びます。
また、出血が認められる場合には、止血効果もある芎帰膠艾湯(きゅうききょうがいとう)を用いることもあります」(岡村先生)
2)妊娠初期~悪阻に有用な基本薬
「妊娠初期の代表的な不調のひとつにつわりがあります。何の問題もない人もいる反面、多くの妊婦さんでは、妊娠5~6週目から12~16週目辺りまで、吐き気や食欲不振などに悩まされます。
原因は現時点ではまだ明確ではないものの、一説によるとhCG(性腺刺激ホルモン)の急激な増加が胃腸の働きを低下させ、つわりを引き起こすといわれています。
つまり、胃腸の機能低下=水分代謝異常(痰飲:たんいん)ということから、小半夏加茯苓湯(しょうはんげかぶくりょうとう)の冷服(水で服用すること)が推奨されています。私の場合、体内の水分の偏在を解消する五苓散(ごれいさん)を第一選択としています。この処方を最初に選ぶメリットは、つわりはもちろん、初期に合併することが多い頭痛や下痢などの症状を伴う方にも有効な点です。
また、つわりは時期や症状によってどの処方を使うとより効果が期待できるかが分かってきており、五苓散はもちろん、六君子湯や人参湯(にんじんとう)など、専門家の目から最適な処方を選ぶことが重要です。
中でも、つわりが長期化すると、元気がなくなります。東洋医学的にいうと生きるための根源的なエネルギーとなる『気』が失われた気虚(ききょ)、巡らなくなる気鬱(きうつ)の状態です。落ち込みやうつ症状の発現などで、メンタルが不安定になることもあります。これに有効なのが、気の流れを良くして吐き気を抑制する半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)と、吐き気を抑制して水分代謝を良好にする茯苓飲(ぶくりょういん)を併せた茯苓飲合半夏厚朴湯(ぶくりょういんごうはんげこうぼくとう)です。長引くつわりには本当に良い処方です」(岡村先生)
3)妊娠後期~分娩に有用な基本薬
「妊娠の時期的にいうと、37週以降41週までは正産期と呼ばれ、母子ともに低リスクの理想的な出産時期とされます。妊娠40週0日が予定日です。つまり、ここからは、赤ちゃんに生まれてほしい時期となります。42週以降の出産では、赤ちゃんの容体悪化や難産の可能性が高まり、また、帝王切開が増える要因にもなってしまいます。
こうした分娩の時期に有用な漢方が五積散(ごしゃくさん)と桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)です。もともと虚証で冷えのある女性の場合、妊娠でさらに冷えが悪化することで骨盤の血流悪化などを生じると、身体がスムーズな分娩を行えない状態にあることもしばしばみられます。そうした際、西洋薬の子宮頚管拡張剤などが使われることが多いですが、併せてあるいは単独で、古くから難産に用いられてきた、温めることで冷えを改善して「分娩に理想的な身体のコンディション」にする五積散が有用です5-9)。
また、桂枝茯苓丸は前編で触れた駆瘀血剤という、体内の余分なもの(瘀血)を排出する作用がある処方で、流産誘発の恐れがあるため妊娠中は慎重投与とされる一方、分娩の促進にも有効10)とされています。このため、妊娠中は慎重投与ですが、分娩時や産後には積極的に用いたい処方です」(岡村先生)
4)産後に有用な基本薬
「産後3か月は血栓症のリスクが高い時期です。これは、体にとって不要なもの(瘀血)がある状態のため、血行促進など血栓症予防を考えることが重要です。また、体内に悪露(おろ:分娩後に子宮の収縮に伴って子宮から排出される子宮内膜や分泌物)が溜まると、その後の体調不良につながります。こうしたことから、血液の巡りを改善し、余分なものを排出する(駆瘀血剤)、分娩にも有用な桂枝茯苓丸が継続して使えます。
近年、産後のメンタルヘルス問題が大きく注目されています。そこで出番となるのが産後の神経症や体力低下に適した芎帰調血飲(きゅうきちょうけついん)です11)。駆瘀血作用を高めた処方が芎帰調血飲第一加減(きゅうきちょうけついんだいいちかげん)であり、エキス製剤では芎帰調血飲に桂枝茯苓丸を加えると近い処方になります。その後に元気がなく(気虚)、貧血症状(血虚)が続く場合は、補中益気湯、十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)、人参養栄湯(にんじんようえいとう)などの補う処方を考えたいです」(岡村先生)
5)その他の産前産後・妊娠時等に関わる基本薬
頭痛(機能性頭痛(※))
「西洋薬のアセトアミノフェンが用いられることもありますが、妊娠後期には使いづらく、無効な場合もあります。そこで頭痛ガイドラインにも載っている五苓散12)や呉茱萸湯(ごしゅゆとう)13)が妊産婦さんにも有効です。特に、妊娠初期はホルモンの変化に伴う頭痛やつわり症状に下痢を併発するケースもあるため、体内の水分の流れを正常化する五苓散は有用な処方です」(岡村先生)
(※)頭痛の原因となる病気がない頭痛
便秘
「酸化マグネシウム等の西洋薬が無効な場合や、特に切迫早産で長期の安静と子宮収縮抑制剤を使用した場合などは大建中湯(だいけんちゅうとう)14)や桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)が役立つことがあります。繰り返す腹痛と嘔吐で数度の絶食入院を繰り返した妊婦さんに大建中湯が有効だったケースもあります15)」(岡村先生)
メンタルケア
「東洋医学の考え方では、『気(き)』というエネルギーが体内を正しく巡ることが重要とされています。それによって各臓器は正常に働き、精神も安定すると考えられています。ところが妊娠中などは気の流れが乱れやすく、イライラや不安などメンタルが不安定になりやすい時期といえます。そうした際に用いられるのが、漢方の代表的な精神安定薬ともいえる抑肝散(よくかんさん)や半夏厚朴湯です。抑肝散は不眠にも有用な処方です。また、これらで効果が得られない、より症状が強い場合には、女神散(にょしんさん)が有効なケースもあります」(岡村先生)
乳腺炎
「基本的に葛根湯(かっこんとう)が中心ですが、化膿性の場合は排膿散及湯(はいのうさんきゅうとう)を用います。メンタルの不安定が見られる場合は「母子同服」(母と子が同時に服用する)にも用いられる抑肝散、元気のない方には前述の補中益気湯などの補剤を使います。このほか、桂枝茯苓丸と五苓散でよくなった方もいます」
効果が出るまでの目安
「服用後効果が出るまでの期間は、処方ごとに異なります。例えば、即効性の高い芍薬甘草湯などは服用から3~4分程度で症状が収まります。一方で、当帰芍薬散のように、慢性的な不調に対する体質改善を目的とした処方は、症状が収まるまでには比較的時間がかかります。
とはいえ、「何となくラクになった気がする!」「少しよくなったかも?」といった効果の兆しは1~2週間程度で現れ、そうでない場合は処方が合っていない可能性を疑います」(岡村先生)
今後の妊娠・出産に関する漢方治療の展望・可能性
最後に、将来的な妊産婦等に対する漢方治療への思いについて語っていただきました。
「ここまで、現代社会の中でバランスの乱れた心身の状態を、妊娠・出産に適した中庸の状態に近づけ、戻していくために漢方が有用であることをお話してきました。今後は、さらなる研究に基づく新たなエビデンスが一つ一つ積み重ねられ、より妊産婦さんが安心で安全に妊娠・出産できる環境が整えられることを望みます。
漢方薬の有用性の周知が進み、妊娠前からの健康づくり(プレコンセプショナルケア)にも活かされるようになれば、『お産のたびに元気になっていく』という新たな価値観への転換も可能で、それは少子化対策の一環にもなるでしょう。そうしたムーブメントの牽引役として漢方薬、東洋医学に期待するとともに、私自身もさまざまな取り組みをしていきたいと考えています」(岡村先生)
(取材・文 岩井浩)
- 参考
-
- 貝原学. 子宮内胎児発育遅延 日医師会誌. 1992; 107(2): 101-104
- 塩田敦子ほか. 漢方薬にて臍帯動脈血流改善、児体重の増加をみた双角子宮妊娠の1例 産婦漢方研のあゆみ. 2017; 33: 99-102
- Nagamatsu, T. et al. Am J Reprod Immunol 2018; 4: e13021. doi: 10.1111/aji.13021
- 柳澤愛実ほか. 当帰芍薬散を含めた集学的治療により安産に至った流死産既往を有する子宮腺筋症合併妊娠の1例 産婦漢方研のあゆみ. 2021; 37: 120-122
- 蔭山充ほか. 「冷え」を訴える子宮頸管未熟妊婦に「熟化剤」としての「五積散」の試みとそのEBM. 産婦漢方研のあゆみ. 2001; 18: 146-148
- 岡村麻子ほか. 漢方薬の内服で冷えが改善し子宮頸管が熟化し陣痛発来につながった10症例 産婦漢方研のあゆみ. 2015; 32: 79-84
- 岡村麻子ほか. 冷えを合併する妊婦における五積散の子宮頚管熟化作用 産婦漢方研のあゆみ. 2016; 33: 74-77
- 岡村麻子ほか. 予定日超過分娩に至った妊婦に対する五積散の臨床的有効性 産婦漢方研のあゆみ. 2017; 34: 38-42
- 岡村麻子ほか. 分娩に漢方薬を導入した4年間の臨床成績―分娩に漢方薬は有効か― 産婦漢方研のあゆみ. 2019; 36: 26-30
- 岡村麻子ほか. 桂枝茯苓丸の内服で冷えを改善することにより有効陣痛を得られた11症例の検討 産婦漢方研のあゆみ. 2018; 35: 173-178
- Ushiroyama, T et al. Efficacy of the kampo medicine xiong-gui-tiao-xue-yin( kyuki-chouketsu-in), A traditional herbal medicine,in the treatment of maternity blues syndrome in postpartum period. Am J Chin Med. 2005; 33(1): 117-126
- 蒲田郁ほか. 当院における妊婦の頭痛に対する五苓散の効果の検討 産婦漢方研のあゆみ. 2022; 38: 87-90
- 光井潤一郎. 妊娠中の慢性頭痛に呉茱萸湯を用いた症例の検討 産婦漢方研のあゆみ. 2021; 37: 81-87
- 中山毅ほか. 妊娠中の便秘症に対する漢方療法の試みー大建中湯および大黄を含有する処方について 産婦漢方研のあゆみ. 2018; 35: 101-106
- 長田佳世ほか. 腹痛・嘔吐で6回の入院を繰り返した妊婦に大建中湯が有効であった1例 産婦漢方研のあゆみ. 2019; 36: 156-159
岡村 麻子(おかむら あさこ)先生
柏の葉レディースクリニック 院長

 QLife漢方 閉鎖のお知らせ
QLife漢方 閉鎖のお知らせ