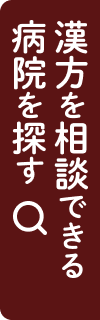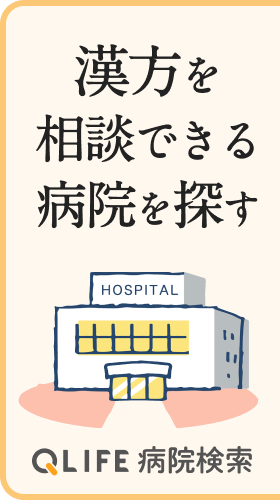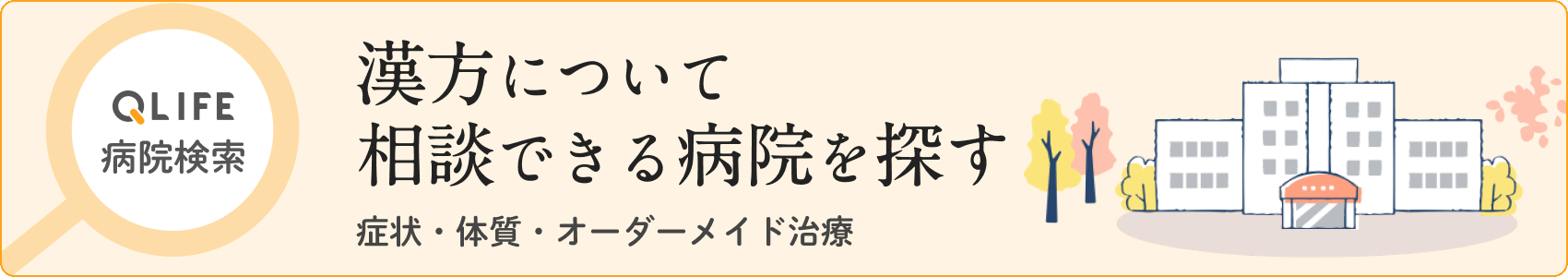せき
公開日:2010.05.31
カテゴリー:病気と漢方
監修:御幸病院ぼたん園施設長 江頭洋祐
原因をつきとめ 早めに対処!
 せきは、気道に異物、ほこり、煙など、なんらかの刺激が加わったときに起こる一種の反射運動で、異物や刺激物を取り除くための防御の役割をしています。
せきは、気道に異物、ほこり、煙など、なんらかの刺激が加わったときに起こる一種の反射運動で、異物や刺激物を取り除くための防御の役割をしています。
せきには「コンコン」という痰の出ない乾いたせき(乾性咳嗽)と、「ゴホンゴホン」という痰を伴う湿ったせき(湿性咳嗽)の2つのタイプに分けられます。乾いたせきは、かぜの初期や急性気管支炎などが疑われます。長い間せきがつづくときは、肺結核の疑いもあります。乾いたせきも、つづくと湿ったせきに変わることがあります。湿ったせきは、かぜや気管支炎の進んだ状態や、肺炎、肺結核、気管支拡張症などが疑われます。痰がでる場合、痰の量や色、粘りなども、病態を見分ける大事なポイントになります。症状を抑えることよりも原因に対する治療が大切となります。
漢方薬にできることは
漢方では咳と痰だけでなく、全身状態と個人の体質とを診て処方が決まります。気道の炎症を抑え、気管をうるおし、せきをしずめる作用を持つ麦門冬湯(ばくもんどうとう)をはじめ、小青竜湯(しょうせいりゅうとう)、柴朴湯(さいぼくとう)、清肺湯(せいはいとう)、滋陰至宝湯(じいんしほうとう) 、滋陰降火湯(じいんこうかとう)などが使われます。熱はあるか、のどが痛むかどうか、くしゃみや鼻水を伴うか、痰が水っぽいか粘り気があるかなど、症状によって薬が違います。
せきをほうっておくと?
慢性気管支炎や肺炎、一部は喘息などになる可能性があります。風邪をひいていないのに咳が出たり、いつまでも続いたりする場合は、重い病気の前兆の可能性もありますから、「たかがせき」と思わず、早めに医師に相談し治療することが大切です。
くらしの中の予防法
なるべく安静を保ち、ガスや灯油ストーブを避け、室内の加湿やこまめな換気を心がけましょう。また、痰が多く出るせきの場合はとくに、十分な水分をとるようにしましょう。タバコを吸っていて咳が続く場合には、まずタバコをやめること。食べ物では唐辛子など刺激物は避けて下さい。
 QLife漢方 閉鎖のお知らせ
QLife漢方 閉鎖のお知らせ