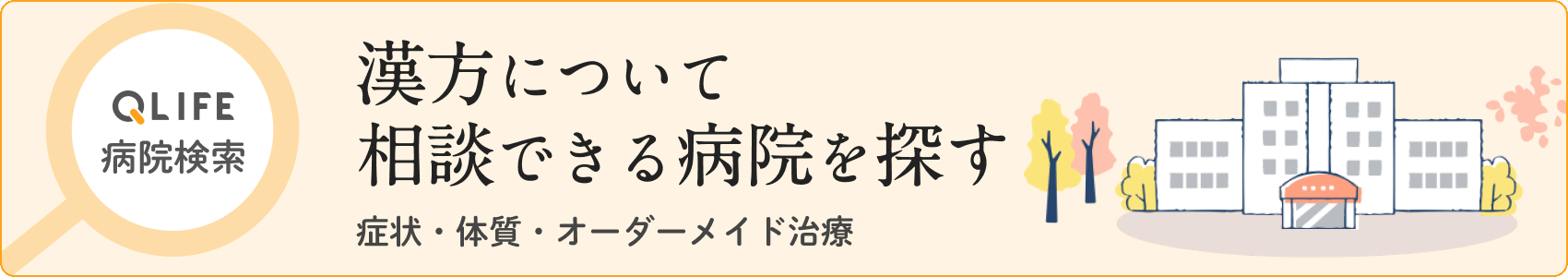がん診療の現場で漢方薬を使用する医師、病院が増加している~国立がん研究センター研究所の調査より

国立がん研究センター研究所
がん患者病態生理分野長 上園保仁先生
がんの薬物治療では抗がん剤が使用され、その副作用に悩まされるケースが少なくないことはよく知られています。抗がん剤にはがん細胞を死滅させる殺細胞効果がある反面、この効果が正常な細胞にまでおよぶ結果、副作用が起こります。最近はこうした殺細胞効果とは異なる分子標的薬と呼ばれる新たながん治療薬も登場し始め、既存の抗がん剤も含めた併用療法で延命効果があることも分かってきました。
しかし、副作用の問題が完全に解決されたわけではありません。むしろ副作用は多様化し、そのコントロールが治療の継続、ひいては延命効果にも大きな影響をおよぼしています。
そうした中で近年、がん治療に伴う副作用のコントロールで、漢方薬が有効な事例もあることが数多く報告されています。国内のがん治療では最高峰に位置する国立がん研究センター研究所がん患者病態生理分野長の上園保仁先生らのグループは、国内の388の中核がん治療病院の緩和ケアチームと、緩和ケアユニット(PCUS)のある161の認定医療施設に所属する医師へのアンケート結果から、過半数を超える6割以上の医師が副作用などのがん関連症状に漢方薬を利用しているという最新事情を明らかにしました。この報告は、既存の治療を補完する、あるいは代替するような新たな医療行為に関する研究を集積する国際的医学雑誌「BMC Complementary and Alternative Medicine」の2012年12月号に発表されました。がん診療の現場で漢方薬の浸透度を調査したほぼ初めての調査結果であり、この結果からがん診療の現場で漢方薬を使用する医師、病院が増加していることが分かりました。
64.3%の医師ががん関連症状の緩和ケアに漢方薬を期待
緩和ケアとは、命にかかわる病気に関して、その病気そのものの治療ではなく、治療に関連する様々な症状や、その病気に罹ったことによる患者さん個人あるいは社会的悩みを改善させ、患者さんが亡くなるまでの生活の質をより向上させることを目的とした医療行為です。がん専門医療機関では従来からこのような取り組みが緩和ケアチームという専門スタッフにより行われており、その他の病院でも都道府県の認可により緩和ケアユニットと呼ばれる専門病棟の設置が認められています。
上園先生らはこうした緩和ケア専門のスタッフを有する医療機関の医師にアンケートを送付し、311人の医師から有効回答(回答率56.7%)を得ました。その結果、64.3%の医師ががん関連症状の改善を目的に漢方薬を使用していると回答しました。
漢方薬を使用する理由としては、「関連症状の治療選択肢としてメリットが大きい」というものが最も多く72%、「他の治療法が有効でない」64.5%、「他の適切な治療が行えない」63.5%で、「患者の要望」は最も少ない23%です。このことから医師ががんの関連症状の治療に漢方薬が有効であると認識していることが分かりました。
漢方薬を使用する症状として最も多かったのが、しびれ/感覚鈍麻の49.5%(使用医師数99人)であり、次いで便秘が38.0%(同76人)、食欲不振/体重減少が36%(同72人)、筋けいれんが35.5%(同71人)、倦怠感/疲労が32.0%(同64人)となっていました。これらの症状はいずれも抗がん剤の使用に伴って起こることが知られている代表的な副作用です。
実際に使用されている漢方薬については、最も多かったのは大建中湯(だいけんちゅうとう)の70.0%(同140人)、次いで牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)の50.0%(同100人)、六君子湯(りっくんしとう)の48.5%(同97人)、芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)の48.0%(同96人)、補中益気湯(ほちゅうえっきとう)の45.0%(同90人)の順で使用されていました。
これらの漢方薬について、医師が50%以上に有効と認識している症状について調査した結果、化学療法の副作用の下痢に対する半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)の有効性に53.4%、補中益気湯の疲労感に56.3%、十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)の疲労感に56.8%、六君子湯の化学療法の副作用の食欲不振に50.0%、抑肝散(よくかんさん)のせん妄に63.3%、芍薬甘草湯は足のけいれんに82.3%、大建中湯は腸のイレウスに78.9%、大建中湯のモルヒネ投与による便秘および腹痛に53.9%に有効と判断していました。
また、漢方薬を処方する重要な動機は、化学療法に対する副作用の緩和とがんの終末期に対するQOLの低下の緩和と80%を超える医師が回答していました。
一方、漢方薬に対する問題点としては、60.7%(173人)の医師が「用量や服用剤形の改良の必要性」を指摘し、これに次いで38.2% (109人)が「有効性に対する科学的根拠がまだ十分ではない」と回答しました。逆にこの2つの部分が改善され、今後さらなる臨床試験による有効性の証明と基礎研究による作用機序の解明により、漢方薬はがん治関連症状の治療でより幅広く使用されるだろうと考えられます。
国立がん研究センター研究所 がん患者病態生理研究分野 分野長

1991年 米国カリフォルニア工科大学生物学部門 ポスドクとして留学
1992年 産業医科大学薬理学講座 助手
2004年 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・内臓薬理学講座 助教授
2010年 独立行政法人国立がん研究センター研究所 がん患者病態生理研究分野 分野長
参考リンク:国立がん研究センター研究所 がん患者病態生理分野
 QLife漢方 閉鎖のお知らせ
QLife漢方 閉鎖のお知らせ